2022.07.20
月に行くには?ロジカルシンキングで考えると?
経営企画グループ T木です。
新年度が始まり、「計画を立てる」ことをしなければなりません。
そんなときに重要なのは「ロジカルシンキング=論理的思考」の力であると思います。
以前に「ロジカルシンキング」には「演繹法」と「帰納法」があるということを教えてもらったことがあり、
今年度の新入社員研修の際には活用させてもらいました。
簡単に言いますと、2つの違いはこんな感じです。
「演繹法(えんえきほう)」は段階的に理論立てて結論を結びつけるもの。
「帰納法(きのうほう)」は複数の推論から結論を結びつけるもの。
なんとなく、帰納法の方が技術が問われる感じがしますね。
そして「えんえきほう」という読み方の難しさから拒否感を感じます。
また、自分が普段やりがちな方法に近いものがあったらいいなと調べてみたところ「仮説思考」というものがあり、
なんとなく「あたり」を付けてから行動して修正しながら結論を導くというものでした。
工程としては、「①現状分析②なんとなく仮説を立てる③検証④修正する」というもので、使用している人も多いのではないでしょうか?
以前、同じような「計画の立て方」で迷ったときに、とある方に「人類はどうやって月に行ったと思う」という問いかけをされたことがあります。 その答えは、「「月に行く」という目標を立ててから、後の計画を立てるんだ」とのことでした。(実際に本当かどうかは不明です) 大きな計画を立案するには、目的・目標が明確でなければならず、そのビジョンを共有しなければならないんだ。と言ってました。 部品一つ一つを作り上げることも重要で、その継続の延長戦上に成功があることも確かですが、全員のビジョンが共有できていることが重要なんですね、 と今更ながら思い返してみた次第です。わりと心に残る話だったのだなと今にしてみると、そう感じます。 また、以前のテレワーク導入計画も思えば、「月に行く」のと同じような計画の立て方だったような気もします。
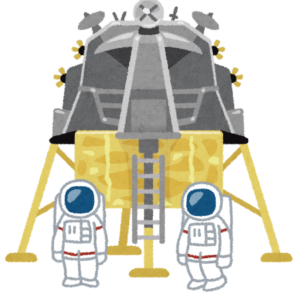
(高所恐怖症でも月レベルであれば関係ない)
たいそうな計画は立案できませんが、ロジカルシンキングの手法を理解していれば、もっと説得力のある提案や計画作りができるかもしれません。
今後も勉強していきたいなと思います!

